華岡青洲ってどんな人?

華岡青洲は、1760年(宝暦10年)10月に紀の川市の旧那賀町に生まれました。
母と妻・加恵の献身的な協力もあって、マンダラゲを主成分とする麻酔薬「通仙散(つうせんさん)」を完成させ、世界で始めて全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した人です。
世界初の全身麻酔手術が、日本で、しかも中央から遠く離れた片田舎で行われたというのは、驚き以外の何者でもありません。
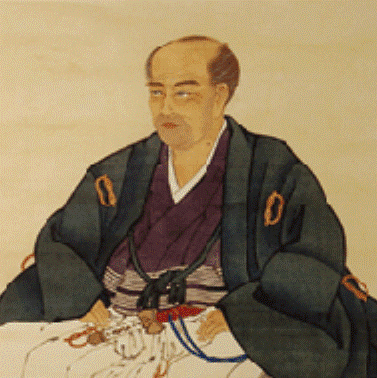
(↑この画像は、ウィキペディアから引用しています)
華岡青洲の生涯
1760年(宝暦10年)に紀伊国(後の和歌山県那賀郡那賀町平山、現在の紀の川市平山)に生まれる。
1782年より京都に出て、外科医大和見水に3年間師事する。見水の師・伊良子道牛が確立した「伊良子流外科」(古来の東洋医学とオランダ式外科学の折衷医術)を学び、1785年帰郷して父・華岡直道の後を継いで開業した。
手術での患者の苦しみを和らげ、人の命を救いたいと考え麻酔薬の開発を始める。研究を重ねた結果、曼陀羅華(まんだらげ)の花(チョウセンアサガオ)、草鳥頭(そううず・・・トリカブト)を主成分とした6種類の薬草に麻酔効果があることを発見。動物実験を重ねて、麻酔薬の完成までこぎつけたが、人体実験を目前にして行き詰まる。
実母・於継と妻の加恵が実験台になることを申し出て、数回にわたる人体実験の末、於継の死・加恵の失明という犠牲の上に、全身麻酔薬「通仙散」を完成。文化元年(1804年)10月13日、60歳の女性に対し通仙散による全身麻酔下で乳癌摘出手術に成功。これは、1846年にアメリカで実施されたジエチルエーテルによる麻酔よりも40年以上前のことであった。
その後、華岡青洲の名は全国に知れ渡り、患者や入門を希望する者が彼のもとに殺到した。また、青洲は、門下生の育成にも力を注ぎ、医塾「春林軒(しゅんりんけん)」を設けた。 また、青洲はオランダ式の縫合術、アルコールによる消毒などを行い、腫瘍摘出術などさまざまな手術法を考案。前述の通仙散の他、彼の考案した処方で現在も使われているものに十味敗毒湯、中黄膏などがある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』華岡青洲にまつわるお話
■垣内池(かいといけ)
華岡青洲は医者としてだけでなく、庶民のためになることに一生懸命取り組んだ人でもあります。
例えば「垣内池」。干ばつと年貢の重さに耐えかねていた付近の住民のために、私財を投げ打ってため池を掘り、「垣内池」と名づけました。
この垣内池は、付近の住民の暮らしを潤したといいます。
